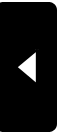2010年11月07日
手挽きの臼の作成 その2
昨日のつづき、
手引きの石臼は、当然ながら手でグルグル回すので、
その把っ手が必要となる。

材料は近所の100円ショップにて、
24φmmの丸棒と、30×40mmの角材、合わせて210円

丸棒を通す穴は、石材用ボーリング(ボール盤)に、木工用の24φmmのビットを付けて、
このビット、100円ショップで525円、
材料より高くついた。


で、 把っ手は、こんな感じで完成。

それから、臼にも把っ手の加工を施し、
今日の作業はここまで。
地区の文化祭まであと6日、はたして間に合うのだろうか・・・
つづく。
手引きの石臼は、当然ながら手でグルグル回すので、
その把っ手が必要となる。
材料は近所の100円ショップにて、
24φmmの丸棒と、30×40mmの角材、合わせて210円
丸棒を通す穴は、石材用ボーリング(ボール盤)に、木工用の24φmmのビットを付けて、
このビット、100円ショップで525円、
材料より高くついた。
で、 把っ手は、こんな感じで完成。
それから、臼にも把っ手の加工を施し、
今日の作業はここまで。
地区の文化祭まであと6日、はたして間に合うのだろうか・・・
つづく。
2010年11月06日
手挽きの臼の作成 その1
ビッキーの幼稚園で毎年12月、恒例のもちつき大会があり、
オイラもほぼ毎年、手伝いをしているのだが、
「大豆を挽いて、きな粉もち もやりたいね、、、」
なんて話を、いつだかしたらしいのだが。。。?
そうしたところ、まさに今、幼稚園の畑では大豆が実り、
なので、大豆を挽く石臼を作らねばならず、
大豆がまだ青い「枝豆」の頃からボチボチ作り始め、
大豆の収穫が近いと聞き、
少し焦って石臼の作成に励む。


大きさは9寸6分(29センチ)園児もグルグルできるように、上臼の厚さ3寸(9センチ)と薄くしてみた。
大豆は油分が多く、目がつまりやすいらしく、
蕎麦用の副溝より太く溝を刻まなければいけないのかな?
その前に、ウチの地区の文化祭があるので、
そこで石臼をグルグル回して、多くの皆様に遊んでもらおうと考えている。
じつは、
手挽きの臼は始めてつくるのであるが、
上手く挽けるか楽しみでもあり、不安でもある、今日の石工職人ヤマグチ
たぶん つづく。
オイラもほぼ毎年、手伝いをしているのだが、
「大豆を挽いて、きな粉もち もやりたいね、、、」
なんて話を、いつだかしたらしいのだが。。。?
そうしたところ、まさに今、幼稚園の畑では大豆が実り、
なので、大豆を挽く石臼を作らねばならず、
大豆がまだ青い「枝豆」の頃からボチボチ作り始め、
大豆の収穫が近いと聞き、
少し焦って石臼の作成に励む。
大きさは9寸6分(29センチ)園児もグルグルできるように、上臼の厚さ3寸(9センチ)と薄くしてみた。
大豆は油分が多く、目がつまりやすいらしく、
蕎麦用の副溝より太く溝を刻まなければいけないのかな?
その前に、ウチの地区の文化祭があるので、
そこで石臼をグルグル回して、多くの皆様に遊んでもらおうと考えている。
じつは、
手挽きの臼は始めてつくるのであるが、
上手く挽けるか楽しみでもあり、不安でもある、今日の石工職人ヤマグチ
たぶん つづく。
2010年11月04日
何さん??

「 痛て~ょ~ 離してくれ~ (>_<。。) 」
今日の本題、
ウチから遠い霊園のお石塔、
何家って読む??
写真を撮り、ウチの者に聞くも、
皆 低学歴、
当然解らず、
そこで、Windows IMEパッド の手書きにて調べたところ、
桒「ソウ」と読む、
なので、「ソウバラケ」なのか??
よく解らず、スッキリしないが、
ここいらで。
2010年11月04日
石臼の怪我 その2
今日は、製粉工場の作業員さんに高い所から落とされ、
大怪我をおってしまった石臼の施術の日、
石臼の天場から石を摘出し、怪我の部分に移植しようと考えたのだが、
安曇野市の石材問屋に、安原石の端材をもらう、
人間であれば、臓器移植と言ったところだろうか。


赤線部分の切除は、

オフカットにて切り込みを入れ、


そしてボーリングにて、均一の深さに穴あけ、


ダイヤモンドカッターにて、粗取り、ダイヤモンドカップにて、平らに仕上げる、


ダイヤモンドカップでは取りきれない隅を、エアーハンマーにて加工、
もらった石を、切除した部分に合わせ切削、
< 写真撮り忘れ >

エポキシ接着剤にて切削した石を接着、


目地はセメントにて、(樹脂系接着剤より、セメントのほうが人体に無害なので)


セメントは、水分が乾燥して硬化するのではなく、
水との科学反応にて硬化する、
なので、水分が蒸発しないように、ティッシュ、布にて養生、
そして毎朝晩、水を補給して、、、
一週間も置けばいいかな?
今日の作業はここまで。
大怪我をおってしまった石臼の施術の日、
石臼の天場から石を摘出し、怪我の部分に移植しようと考えたのだが、
安曇野市の石材問屋に、安原石の端材をもらう、
人間であれば、臓器移植と言ったところだろうか。

赤線部分の切除は、
オフカットにて切り込みを入れ、
そしてボーリングにて、均一の深さに穴あけ、
ダイヤモンドカッターにて、粗取り、ダイヤモンドカップにて、平らに仕上げる、
ダイヤモンドカップでは取りきれない隅を、エアーハンマーにて加工、
もらった石を、切除した部分に合わせ切削、
< 写真撮り忘れ >
エポキシ接着剤にて切削した石を接着、
目地はセメントにて、(樹脂系接着剤より、セメントのほうが人体に無害なので)
セメントは、水分が乾燥して硬化するのではなく、
水との科学反応にて硬化する、
なので、水分が蒸発しないように、ティッシュ、布にて養生、
そして毎朝晩、水を補給して、、、
一週間も置けばいいかな?
今日の作業はここまで。